肺ガンとタバコの因果関係を考える〈下〉─愛煙家通信CONFORT 2015 Autumn No.14

出典:愛煙家通信CONFORT 2015 Autumn No.14(ワック株式会社)
愛煙家通信Web版

この著作の引用は、「葉巻は体に害があるか?(https://cubancigar.jp/blog/archives/5024)」の記事における、葉巻の害に関する考察において、重要な根拠となる内容であるため引用掲載するものです。著作権は、著作者に帰属します。
肺ガンとタバコの因果関係を考える〈下〉
「受動喫煙」説のいかがわしさ
秦郁彦(現代史家)目次
前回〈上〉(13号・6月12日発行)の概要
肺がんの原因がタバコであるとする「証拠(エビデンス)」が固まらないうちに、疫学統計を根拠に嫌煙・分煙が叫ばれるようになり、全面禁煙への風潮が世界的に広がった。しかし、タバコを肺ガンの原因と決めつけるには、「喫煙率と肺ガン死の統計」「部位別のガン死亡数と順位」「肺ガン関連数値の変遷」などのデータから、肺ガン死と喫煙率が反比例していること、非喫煙者の肺ガンが増えていることなどの疑問が生じるが、これに対する説得力ある反論は出ていない。
では、現在、声高に叫ばれている受動喫煙説の位置づけはどうなるのか。非喫煙の罹患者はすべて受動喫煙の被害者なのか。「世界の反タバコ運動に投じた巨「大な灯」(青木国雄)、「いかがわしい宗教の経典に似ている」(名取晴彦)と両極端の評価がある平山雄の受動喫煙説を、今回は再検分する。平山コホートの転変
まずは極端に評価が割れる平山雄(故人)という特異な医学者の来歴を、年譜風に見ていこう。
一九二三年 平山遠(満州医大外科教授)の長男として京都に生れる。
奉天第一中学校、旧制一高を経て、
一九四六年 満州医科大学卒。
一九四七年 厚生省国立公衆衛生院技官(疫学部)。
一九五一年 医学博士。
一九五一─五二年ジョンズ・ホプキンス大学留学、五九─六〇年米国留学、六三~六四年WHO勤務(インド駐在)。
一九六五─八五年 国立がんセンター研究所疫学部長。
一九八一年一月 英国の医学情報誌BritishMed-icalJournal(以後はBMJと略称)に論文発表。
一九八五年 予防がん学研究所を設立・所長。
一九八九年 第一生命相互会社より保健文化賞。
一九九五年 十月二十六日ガンで死去。この経歴で目を惹くのは、平山が一九四二年九月に旧制一高(理乙)を卒業したさい、ほぼ全員が東京帝大医学部へ進学したのに、一人だけ満州医大へ進学したことで、同級の林滋生(のち国立予防衛生研所長)は「稀な例だが、お父さんが満州医大教授だったからと聞いた」と語る。
終戦と同時に医大は中国に接収され、学生は四六年から四七年にかけ内地へ引き揚げ、内地の医大へ転入した。医大同期(第十九期)の多比良勉医師は卒業式なしに四五年十月に学長名で卒業証書をもらったが、日本で医師国家試験を受け医師免許を得た時は四六年卒として認定されたと語る。旧制高校の同期生は四六年九月に医大を卒業しているので、それに合わせたものであろうか。
厚生省の公衆衛生院に技官として入ったのは、一緒に引き揚げてきた父の遠が国立長野病院長に就任したので、その縁故かと思われるが、医局やインターンとしての臨床経験を持たなかったことは、彼の進路と視野を狭めてしまう。そのなかで平山は、占領軍が持ちこんだアメリカ流の公衆衛生、なかでも新興の疫学分野に活躍の舞台を見出す。伝染病、結核、ガンと疫学調査の重点は移っていくが一九六五年、新設の国立がんセンターに転出すると、彼は同年末の国勢調査にあわせ、厚生省の補助金をもらって、大規模なコホート(co-hort)調査のプロジェクトを立ちあげた。
コホートはローマ軍の隊列を意味するが、この調査では「環境ならびに習慣性諸因子など人とがんとの関係(26)」を将来にわたり追跡観察するのを目的とした。平山コホートの概要は表4を参照されたいが、十四年かけて二十六万人余を追うのは世界的にも前例を見ない規模であった。
戸籍と住民登録制度が完備している日本だからこそ可能だったし、国勢調査に便乗して保健所のスタッフが各戸訪問で調査表を回収した。当初の調査項目は食習慣(コメ、魚肉類、緑黄野菜、ミソ汁など)、嗜好品(タバコ、酒、茶など)で、十四年間の死亡原因別にその関連性を検討したのであるが、とくに喫煙については開始と中止年齢、喫煙量、性別などを詳細に記入させた点から見て平山が肺ガンとの関連を重視していたことが推量できる。
公衆衛生院時代の同僚だった重松逸造博士(のち疫学部長)は「一九五五年頃か平山君は喫煙と肺ガンの問題に興味を持っていたが、直接には六四年に米公衆衛生総監部が発表した報告書がきっかけだった」と語り、「本人はタバコを吸おうとしていたが、体質に合わぬのか、むせちゃってだめなんですね」と笑った。
重松が回想したように、喫煙が肺ガンのリスクを高めているとす先行報告は珍しくなく、英国人医師三万余人を対象としたドールや三六万人を対象としたハモンド(米)の調査が知られていた。わが国でも、肺ガンと喫煙の因果関係に着目する研究報告は少なくなかった。とくに浅野牧茂(公衆衛生院)は、前記のリッキントに触発され、「受動喫煙」(passivesmoking)の被害分析に取りくんでいたが、対象は職場、乳幼児、胎児への影響に絞られていた。(27)
十四年にわたるコホート調査の膨大な材料をかかえ、何か新機軸となるテーマはないかと考えていた平山にひらめいたのが、喫煙する夫からの受動喫煙で被害を受けている非喫煙妻という目新しい側面を引きだすことだった。しかも彼は劇的効果を狙ってか発表の場を日本ではなく、イギリスの医学情報誌(BMJの一九八一年一月十七日号)を選んだのである。
いつごろ彼がこのテーマを着想したかは、はっきりしない。平山はすでに啓蒙書を主とする著書を数冊書き、英文の論文も執筆していた。なかでも一九八〇年は多産で『がんの計量疫学」では手がけてきたコホート調査の要点を紹介しているが、喫煙のリスクを喉頭ガン(首位の一三・六倍)、肺ガン(三・六倍)、胃ガン(一・五倍)、全ガン(一・六倍)と並べている。また飲酒のリスクを口腔がン(三・五倍)、クモ膜下出血(二・四倍)、肺ガン(一・三倍)と列挙し、受動喫煙にはまったく触れていない。(28)
前後して刊行した『流行するタバコ病』(一九八〇)の序文に、全ガンよりリスクの低い胃ガンで死んだ越路吹雪が「六〇本もタバコを吸っていたから」と書いたのは、この人特有の早とちりだろうが、やはりデータを生かす方向性をまだ決めかねていた事情がかいま見える。
受動喫煙の問題意識を持った動機について、平山は「ヘビースモーカーの夫を持つ非喫煙の妻たちは肺ガンの高いリスクを持つ日本からの研究」と題したBMJ論文の冒頭で次のように述べている。
(コホート調査で)多数の非喫煙妻たちが、喫煙する夫からの受動喫煙によって肺ガン死するリスクが二倍にもなることが明らかになった。(中略)肺癌の年齢調整死亡率は、日本で男性も女性もともに急激に増加してきた。肺癌になった日本女性で喫煙者はごく少数(only a fraction)なのに、なぜ彼女らの肺癌死亡率が、男性と平行しているか不明だった。本研究は、この長年の謎の少なくとも一部について説明できるように思われる。(29)
平山論文の要点は表4の通りだが、核心のⅡ「非喫煙妻の肺ガン死と夫の喫煙習慣」で九万人余の非喫煙妻の十四年間(一九六六─七九)における肺ガン死は、夫が非喫煙者の場合は三二人、喫煙者の場合は一四二人である。人口比で見ると前者は〇・一五%、後者は〇・二〇%だから僅差に見えるが、平山式の計算では相対リスクは一・六一倍と二・〇八倍の有意差を示すとされる。(30)
そして欧米に比し喫煙率の低い日本の妻たちの肺ガン死が多いのは、受動喫煙によって説明できると結論したのだが、海外専門家たちの反響は必ずしも好意的ではなかった。むしろ批判の声のほうが強かったと評してよい。
BMJには一九八一年だけで、平山論文に対するコメントが十二本も掲載されているが、ほとんどは疑問か異議の部類で、平山自身も三本の反論を送っている。(31)異例と言ってよいが、一九八四年四月には七人の専門家がウィーンに集まり、「受動喫煙に関する国際円卓会議」を開催する。平山も追跡期間を二年延長した第二論文を提出、討議にも加わったが、議事記録を通読すると孤軍奮闘する平山を吊し上げる会かと思えなくもない。(32)
ウィーン会議では物別れ
こうした平山論文に対する批判は多岐にわたり、詳細を紹介するのは煩にすぎるので、ここでは代表的な論点を要約して次に列挙したい。
(1) 基本データの取得は一九六五年に限られ、転居者をふくめ、その後の追跡が不十分である。対象地域の六府県が公害の多い工業地帯に偏していないか。
(2) 夫妻の住宅環境、同居時間など受動喫煙に関わる諸条件を調査していない(平山は日本の住居は狭苦しいと釈明)。
(3) 肺ガンが原発か転移か、組織型(腺ガンか扁平上皮ガンかなど)の別などが不明。
(4) 「ときどき吸う人」の一〇万人当り二六四人という死亡率が、「喫煙しない人」の三〇四人より低いというデータを無視している。
(5) 非喫煙者同士の夫妻でガン死した実数と原因(タバコ以外?)が究明されていない。
(6) 既婚女性より未婚女性の肺ガン死亡率のほうが高いなど理に合わぬデータがあるのは、十四年間の肺ガン死が計三四六人と過少にすぎるなど、偶然性に左右される要素が多いからではないか(平山は未婚女性の多くは未亡人だと反論)。
(7) 副流煙はすぐに希釈拡散し、口からではなく鼻から吸入するので濾過される。
(8) 相対リスクが一~二では有意性があるとは言えない。(33)被調査者の五%がウソを申告すると、がらりと変ってしまう。ウィーンの円卓会議で問いつめられた平山は、短いBMJ論文に記載していなかった情報を持ちだし、検証のしようがないと不満を買ったが主張は変えず、「一日五本でも肺ガンになる」式につっぱねた。ガーフィンケル博士が「平山博士は肺ガンと受動喫煙の関係をprobableと言ったが、私はpossibleと言い直したい。肺ガンと能動喫煙までなら折りあえるが」と食いさがるや、平山は「タバコを廃絶したら、こんな論争は不要になる……私はprobableの線で政府とWHOへ働きかけたい」と突き放した。
最後に座長のレーナート博士が「平山理論は一貫性がなく、科学的証拠に欠ける仮説にとどまる」としめくくったが、「今後も社会問題として論争はつづくだろう(34)」と予告するのを忘れなかった。この予告は的中する。
これだけ多くの苦情が出た論文も珍しいが、コホート開始時に受動喫煙というテーマを想定していたら、平山はより適切な応答を用意できたのではあるまいか。あるいいは名取春彦が言うように、集計の最終段階で「タバコを吸わない人も大勢が肺ガンになっている。平山ははたと困った。辻棲が合わなくなる。それで〈受動喫煙〉という言葉をつくって、タバコを吸わない人も実は吸っていたのだということにした(35)」のかもしれない。
しかしレーナートが危惧したように、平山理論を歓迎する動きも出た。「公衆衛生における新分野を開始した画期的な成果」(オング、グランツ)と賞讃する医学者もいたし、一九八二年の米公衆衛生総監部の報告書も好意的関心を示す。
平山論文に刺激されて各国で類似の手法による追試も試みられたが結果はまちまちで、「一九九〇年までの25の研究のうち…13は統計学的に有意」と、第二次たばこ白書(一九九三)は観察した。半信半疑というところだろうが、意外にも平山が所属するがんセンターが「受動喫煙によっても、肺がんのリスクが高まる可能性が示唆された(36)」と及び腰だったのは興味深い。
内外の追試はその後もつづいているが、六二例のうち五〇例は有意差がないとする評価(37)もあり、IARC(国際がん研究機関)のように、一九九八年に「リスクは1・16で有意差なし」と判定していたのが、六年後には「受動喫煙は肺ガンをひきおこす証拠がある」と豹変する例も珍しくなかった。おたがいに都合の悪い結果が出ると、データを改竄しているとか、タバコ会社にカネをもらっていると叩きあうので、専門家でも見きわめがつきにくくなっている。
ところがガン撲滅と反タバコのキャンペーンに乗り出していたWHO(事務局長は中嶋宏、一九九八年からブルントラント)にとって、受動喫煙の害を強調する平山理論は追い風となる好材料であった。
その波に乗って平山理論は日本に逆輸出され、禁煙運動家の間で「神の福音のように(38)」(ヴォス)もてはやされることになるが、母国の医学界では平山が発表と討議の場をもっぱら海外に求めた事情も手伝って、そっけなく扱われた。一〇年ごとに発行される古巣の国立がんセンターの記念誌でも、一九八五年に定年退職したのを機に、平山関連の記事は見られなくなる。
孤立した形の平山は、予防がん学研究所と予防老化学研究所を設立、『禁煙ジャーナル』を主宰する禁煙運動家として全国を飛びまわり、次々に啓蒙書を出版するが、しだいに過激度を増していく。その一端は、
『喫煙流行の制圧』(一九八〇)
『たばこはこんなに害になる』(一九八四)
『菜食・禁煙・がん予防』(一九八八)
『ガンにならない体をつくる』(一九九一)
『ベータ・カロチン健康法』(一九九四)
『ガンにならない健康食』(一九九五)のような著書名で見当がつこう。
運動家としての平山の論調は、切れ味の良さ、科学者には稀な断定調、キャッチフレーズの巧みさが持ち味であった。「日本専売公社(現JT)はタバコ病専売公社と改名せよ」とか「その一服、一服ごとに、ガン育つ」とか「残留喫煙者は社会のドロップアウト、毒蛇のようなもの」といった言行が残っている。
勢い余って「タバコは肺ガンばかりではない。ほとんどのガンはタバコが原因」と叫ぶようになるが、晩年にガン予防へ有効だと推奨したベータ・カロチンを含む緑黄色野菜の摂取は、アメリカのコホート調査で、逆に発ガン性ありと結論が出て困ってしまう一幕もあった。
サンプルとして、一九九二年に広島県医師会館で開催された第九回全国禁煙教育研修会における平山の特別講演の一部を抜いてみよう。
医師会が禁煙の先頭に立つのを待ち望んでいた。肺ガンの罹患率が一〇万人対一〇七人というと、宝くじに当るようなものと言う人がいる。しかし生涯率で見ると、これの一〇〇倍になる。一日五〇本以上吸う人は七十五歳までに肺ガンで一〇万人につき三万三千余人が死ぬ。ちょうど三分の一だ。残りの人がなぜならないかというと、肺ガンになる前に心臓病などで死ぬからである(中略)。
肺ガンとライフスタイルの関係ではタバコが横綱、酒は大関、どの部位のガンでも筆頭、妊婦が喫煙するのは胎児に対する密室殺人、副流煙は毒ガス、米厚生長官は“喫煙は緩慢な自殺”と言ったが、私は受動喫煙を“緩慢なる他殺”と呼びたい。(39)
「鬼面人を驚かす」の見本と言えそうな論調だが、見逃せないのは傍点を付したように本来は中立的な統計数字を露骨な我田引水的論法で歪めて、聴講者の恐怖心を煽りたてていることである。天災の到来を予言する新興宗教の教主もどき、と言ってよいだろう。
平山は一九九五年に肝臓ガン(一説には肺ガン)で没したが、その後の禁煙運動に多大な影響力を残し、とくに「受動喫煙の問題では理論的な支柱(40)」(渡辺文学)としての役割を失っていない。ひとつにはWHOや先進諸国の圧力で、喫煙規制の強化に踏み出さざるをえない日本政府が、それを正当化する根拠として平山理論を必要とする事情もありそうだ。
次に肺ガンと喫煙の関連をめぐって、最近の約二十年間に起きた医学上、政策上の論争経過をたどり、あわせて将来的な展望に及びたいと思う。
疑わしきは罰すWHO路線
この論争で発言する医学者は病理学系統と疫学系統に分れ、それに学会活動家が加わる構図と見受ける。いずれも少数で、大多数のガン専門医は診断と治療に忙しく、その面での技術開発には熱意を持つが、ガンと喫煙の関連性のようなテーマには関心が薄く、受け売りですませているようだ。東大医学部の教科書に指定されている『標準呼吸器病学』(二〇〇〇)は、次のように記述している。(41)
肺癌は圧倒的に高齢者の癌である。肺癌と喫煙の関連性が強調されている。しかし実際に喫煙との関連性が疑われているのは扁平上皮癌だけである。
一方、近年、扁平上皮癌は著減し、喫煙とは関連の少ない腺癌が圧倒的に多くなってきている……わが国だけでなく、欧米においてもみられていることであり、呼吸器疾患における禁煙の重要性は肺癌においてはCOPD(注:肺気腫など)よりは低い。
簡にして要を得た冷静な解説だが、さらに踏みこんだ須田健一らによる二〇〇九年の連名論文を見ると、「喫煙が肺癌の原因であることはゆるぎない事実として一般にも広く認識されている」としながらも、わが国の肺癌死亡者のうち男性の三一%、女性で八〇%が喫煙に起因していないのも事実で、「非喫煙者の肺癌の原因は未だはっきりとは同定されていない」と認識する。
そのうえで非喫煙者の肺癌の発症に関わる複数ないし未知の因子として、次のような候補を列挙している。(42)
1 環境喫煙(ETS)──主に受動喫煙を指すが、寄与度はさほど高くない。
2 職業的・環境的発癌物質──大気中の粉塵、放射性物質、アスベスト、台所の調理油からの揮発蒸気など。
3 エストロゲン──とくに女性ホルモン。
4 遺伝的因子──肺癌家族歴(一・五倍説も)、DNA修復能力の低いことなど。
5 大気汚染、肉食などの食事因子。
6 その他。これを見てもわれわれがもっとも知りたい諸因子の比較寄与度は、数十年前と同様に判然としないことがわかる。たとえば大気汚染は「その他」のひとつに押しやられているが、浅村尚生は「大気汚染の深刻化」を重視しながらも「じつは、はっきりしたことはまだわかっていません(43)」と逃げている。
おそらく病理学系の医学者たちには「肺癌も遺伝子異常や薬物代謝酵素活性の違いなどにタバコを始めとした種々の発癌性物質が複雑に組み合わさって発生する(44)」(阿部作)といったところが現時点の公約数的見解ではあるまいか。
ついでに疫学系の観察も挙げておくと、平山コホートを援用しつつも、「肺がんが最も好発する年齢群のヘビースモーカーでも、93%の人は肺がんにならない」ので「喫煙者全員に禁煙を求める「必要はない」のに「どのスモーカーが肺がんになるかを予め識別できなかったために全員が禁煙(45)」を強いる風潮にしてしまったと説く重松逸造のユニークな視点が興味深い。
そして「疑わしきは罰す」流れにしてしまったのを悔いる重松は、遺伝子解析などを含む分子疫学面における患者対照研究の発展で識別を可能にしたいと提言するが、見通しは必ずしも明るくない。理由は少なくとも二つある。
第一は、在来型の動物実験が行きづまりを見せていることだろう。第二次たばこ白書には、ここ半世紀にわたる「たばこの発がん性に関する動物実験の一覧表」(外国四一例、日本一六例)が提示されている。(46)
タール塗布や強制喫煙が主流だが、「ビーグル犬の気管を切開して、紙巻きたばこを二年半にわたって強制喫煙させたところ、二四頭のうち二頭に微小扁平上皮がんを認めた」とか「マウスへの強制喫煙を六〇〇日間続けて初期腺がんの発生を認めた」という極端なものが多く、「こんな状態で副流煙を吸い込むことはありえない(47)」と評されても、しかたがあるまい。白書もこの手法は「極めて困難」とあきらめ気味である。
第二に、嫌煙運動の拡大、行政の干渉で喫煙可能な空間がしだいに狭められた結果、受動喫煙の「被害者」が急減しつつあり、平山流のコホート調査はやろうと思ってもできないという皮肉な現象が起きた。第三次たばこ白書が「六府県コホート研究」の見出しで平山の調査データを改めて大々的に取りあげたのも、比肩する後継コホートが見当らなかったせいもあろう。(48)
だが白書は禁煙者増でコホートの条件が成り立たぬことや、ヒトと同条件での動物実験に見込みがないと認めながら、因果関係について水俣病裁判や明治日本の脚気論争を引き合いに出す。
疫学的手法に拠った高木兼寛(海軍省医務局長)らの主張に、病原や病理の裏付けがないとして反対、脚気の予防が進まなかった例になぞらえ、「最も説得力があると判断された因果関係の仮説」をとりあえず受け入れるべきだという論理を展開した。「疑わしきは罰する」路線への伏線と言えよう。
厚生省が「健康21」のプロジェクトを始動させた二〇〇〇年前後は、政策的な転換点となる。第一次(一九八七)と第二次(一九九三)のたばこ白書で「喫煙と肺がんの因果関係は多くの疫学的研究および実験的研究でほぼ確立してきているとみられる」(同文)と揺れていたのが、第三次たばこ白書(二〇〇二)では「肺ガンはたばこが原因の大部分を占めている(49)」と断定するにいたる。中立的立場を捨てたと言えよう。
前後して厚労省の影響下にあった日本肺癌学会(二〇〇〇)、日本公衆衛生学会(二〇〇〇)、日本癌学会(二〇〇三)、日本医師会(同)が、次々に「禁煙宣言」を声明した。一部の急進的な会員に突きあげられてか、反タバコ、反受動喫煙のスローガンを打ち出すところもあった。
このような突きあげは、その後もつづく。一例を挙げてみよう。肺癌学会の機関誌である『肺癌』誌に掲載された女医の提案で、WHO声明と平山提言にならい、(1)会員は社会のロールモデルとなるよう禁煙せよ、(2)会員の喫煙事情やタバコ規則への態度を調査する、(3)タバコ会社と縁を断つ規定を新設する、(4)タバコ規制活動への積極的参加、など十四項目を並べている。
そして受動喫煙対策として喫煙所の設置(分煙)を推奨している学会の禁煙宣言を取り消し、完全無煙化へ向け行動することを宣言せよと迫る。(50)
有無を言わせぬ過激さに私が連想したのは、WHO事務総長時代に華々しい活躍ぶりを見せ、「世界の環境大臣」の異名をもらったグロ・ブルントラント(小児科医出身の元ノルウェー首相)であった。彼女は平山雄に似た科学者らしからぬレトリックの巧者で、「二〇世紀には約一億人がタバコ関連病で死んだ」とか「世界中のどこかで十三秒に一人の喫煙者が死んでいる」たぐいの発言でマスコミを賑わせ、WHOを強力な政治団体へ変貌させた。
一九九九年の総会で「たばこ規制枠組条約」を提案したブルントラントは、立ちおくれている日本にハッパをかけようと、その年にWHOの国際会議を神戸で開催する。会場をのぞいた斎藤貴男の報告によると、参加者の九割が女性で「フェミニズム大会にも似た雰囲気が漂っていた(51)」という。
そしてタバコは「絶対的な悪」という前提で、会議は「どうすれば規制を進められるかという運動論ばかりが語られた」ことに、斎藤は「個人的な嗜好に、WHOという国際機関が介入する。タバコの害のメカニズムが解明されたとは言えない現状で、禁煙以外の道を認めない空気」に違和感を抱くが、どうやら大勢は決した感があった。
次は酒かケイタイか?
さて二十一世紀に入ってからのタバコ政策はWHOの圧力に各国が押し切られる形で、警告→分煙→禁煙→全面禁煙(勧告→法的強制)の流れを急加進させつつある。
二〇〇五年に発効した「たばこ規制枠組条約」(FCTC)は次のような条項を掲げた。
(1)価格および課税に関する措置(値上げ)。
(2)職場や公共の場所での喫煙規制。
(3)パッケージへの警告表示。
(4)広告や販売促進などの禁止。
(5)未成年対策として自動販売機の規制。建前としては各国の主権を尊重するとはしているものの、その後の締約国会議で実現度をチェックして約束を迫られるため、日本政府も追従せざるをえなくなった。タバコ財源確保のため消極的だった財務省も、厚労省が主導した健康増進法(二〇〇三年発効)との挟み打ちにあい、抵抗をあきらめた感がある。
二〇一〇年の時点でわが国でのの達成度を眺めると、(1)では一九九八年から、二〇〇三年、二〇〇六年と約一割ずつ値上げされ、二〇一〇年十月に「史上最大の幅」の四割値上げが実施されて、二〇一四年四月には消費税増税にともない一〇円~二〇円の値上げとなった。
(2)では、ばらつきはあるが職場、病院、学校、交通機関の建物内禁煙とともに、条例による路上、飲食店、タクシーなどの禁煙が広がり、分煙の主旨による喫煙所も撤去されつつある。
(3)の警告表示は、「喫煙は、あなたにとって肺ガン(注:心筋梗塞、脳卒中、肺気腫の四種を交互に)の危険性を高めます。疫学的な推計によると……非喫煙者に比べて約一七倍高くなります」の文言がパッケージに印刷されている。
(4)(5)の詳細は省くが、(5)についてはタスポ・カードの導入で面倒がる喫煙者がコンビニへ移ったため小売店の廃業をもたらした。
注目されるのは(3)で、心筋梗塞など新顔の三種を加えている点である。肺ガン絶滅の見通しがつきそうもないので、とりあえず標的を他の病気にも分散させる狙いだろうが、狂信的な健康絶対主義者が巣食うWHOはタバコ追放運動に一応のメドがついたので、次のスケープゴートを模索しているように見える。
次の標的はアルコールの規制だろう。「年二五〇万人の死にかかわるアルコールは健康だけでなく社会悪」ととらえる観点から、各国に販売や広告の自主規制を求め、二〇一〇年には「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」が第六三回WHO総会において全会一致で採択された。
フーバー大統領が「高貴なる実験」と呼んだアメリカの禁酒法(一九二〇─三三)をめぐる表裏の歴史を書いたマーク・レンダーは、「失敗の教訓のすべてを、再び学びなおす過程にあるのかもしれない(52)」と危惧しているが、一部の医学者や運動家は「百薬の長とはいえ、よろずの病は酒からこそ起こる」と喝破した兼好法師の後段部分を証明する作業に熱中するだろう。
ちなみに最近は泥酔者が減ったと感じているが、そうでもないらしい。新聞報道によると、二〇〇九年に警察が保護した酔っぱらいの総数は七〇〇三八人(うち女一七〇八人)で、一〇年前に比べ三割増(女は四割増)だという。ターゲットにされてもおかしくない統計ではある。
医療費増や酔っぱらい運転による事故などの社会的コストを計算していくと、タバコを上まわるリスク値が算出されるかもしれない。だが往年の禁酒法が密造、密輸、もぐり酒場やギャングの横行をもたらしたように、「酒とタバコ」に対する人間の伝統的渇望を法的規制や迫害で押さえつけるのは不可能に近いと思われる。
アルコールに次ぐ標的は、他にもある。電磁波(ケイタイ電話)、香水、ファストフード、コカ・コーラ、肉類、肥満(メタボ)、そして最後の難物である自動車などがずらりと控えている。
電磁波が候補になっていることに首を傾げる人もいようが、実は例のブルントラントが関わっている。二〇〇二年にノルウェーの新聞が一面トップで紹介した記事によると、彼女はタバコの煙と電磁波に過敏な体質の持主で、WHO事務総長室に入るスタッフはケイタイをオフにするよう厳命していたという。
彼女は最後の大仕事を電磁波規制と宣言していたが、その成果かと思わせるニュースがあった。ストックホルムのカロリンスカ研究所(ノーベル医学賞の認定事務局)は、一九九七年からスウェーデン国民の健康指標が急激に悪化しつつあるのは、その年から爆発的に普及したケイタイの容疑が濃いと発表したのである。(53)
酒もタバコもやらぬ菜食主義者のヒトラーがひきいるナチス・ドイツは、権力で病的人間を排除する「健康ファシズム」国家をめざした。昨今のとどまるところを知らない健康志向の風潮は、国際機関や国家が個人の自己決定権を否認して介入を強めていく点で、ナチスの思考法に似ていると危ぶむ人か少なくない。しかも、その過程であやふやな医学的根拠をふりかざした非同調分子への差別や迫害を、当然とする空気が形成される。
近代日本の医学は感染症、ついで結核の制圧に成功し、世界一の長寿国家となり、残された目標はガン、心臓、脳血管の三疾病に絞られてきた。その克服に向け、多大のエネルギーとコストを投入しているが、効用の限界に近づきつつあるようにも見える。
ガンをもし絶滅できたとしても「平均寿命を二年ないし三年延ばすことができる(54)」程度だとすると、そろそろ思考の転換を考えてよい時期にさしかかっているのではあるまいか。
〔柱〕
(26)『国立がんセンター年報』第7号(一九七五─七四年度)四七ページ。
(27)浅野牧茂「PassiveSmoking―その環境と生体影響」(『医学のあゆみ』「一九七七年十一月五日号)、同「受動的喫煙」(『からだの科学』「一九八〇年十一月号)。
(28)平山雄編『がんの計量疫学』(篠原出版、一九八〇)一八ページ。
(29)Takeshi Hirayama,Non-smoking Wives of heavy smokers have a higher risk of lung cancer, a study from Japan(accepted13 Nov. 1980),British Medical Journal vol. 282, 17 Jan. 1981, p.p.183-85
(30)平山雄「喫煙の臨床的意義」(『日本医事新報』「一九八〇年八月三十日号、一六─一七ページ)。
(31)BMJ, Vo1. 282-283, p.p.733,914-17, 985, 1156, 1464-66
(32)Preventive Medicine 13, p.p.559-746(1984)
(33)平山は一九八四年の第二報告(Preventive Medicine 13,p.p.680-90)で相対リスク値を1・4~1・6および1・91と修正、竹本忠雄は有意差なしの1・3と1・5に修正すべきだと主張した。
(34)Preventive Medicine13, p.746
(35)前掲名取、五二ページ。
(36)『国立がんセンター二〇周年誌』(一九八三)一七八ページ。
(37)『たばこの事典』(TASC、二〇〇九)一七七ページ。
(38)Tage Voss, Smoking & Common Sense: One Doctor’s View, London, 1990)の邦訳は「たばこ──ホントの常識』(山愛書院、二〇〇三)一三〇ページ。
(39)「愛媛県医師会報」、「一九九二年九月号(文責は真鍋豊彦)。なお傍点部分の数字には疑問が多い。『がん統計’13』によると、肺ガンの生涯罹患リスクは男九・五%(一〇人に一人)、女四・三%(二三人に一人)、同じく生涯死亡リスクは男六・一%(一六人に一人)、女二・二%(四六人に一人)である(二三~二四ページ)。実数では一九九〇年の全死亡約八二万人に対し、肺ガン死(全年齢)は三・六万人である。一日五〇本以上のヘビースモーカーはその一割以下であろう。
人口一〇万比を利用して錯覚させる手法はその後もあちこちで見かける。たとえば「人口10万人当たりの生涯リスク(死亡)は、高い順に1位は能動喫煙3万7500~5万人、2位が受動喫煙(家庭内)5000人……3位は交通事故で480人」(『毎日新聞』一〇年四月三十日付の本田宏〈医師〉論文)も、その一例である。数字の根拠も不明だが、一〇万人のうち五万人以上、つまり半分以上がタバコに起因する肺ガンで死ぬと錯覚させるトリックと言えよう。
(40)渡辺文学(『禁煙ジャーナル』編集長)『タバコの害とたたかって──スモークバスター奮戦記』(大日本図書、一九九六)。
(41)泉孝英編『標準呼吸器病学』(医学書院、二〇〇〇)四一六ページ。
(42)須田健一、小野里良一、光富徹哉「肺癌の原因──喫煙と環境因子」(『臨牀と研究』86巻7号(二〇〇九)。
(43)浅村尚生『肺ガンの最新治療』(講談社、二〇〇二)二八ページ。
(44)前掲阿部、八ページ。
(45)重松逸造『追記集─疫学研究50年抄』(非売品、二〇〇三)八四ページ。
(46)前掲第二次たばこ白書、五八─五九ページ。
(47)斎藤貴男「禁煙ファシズムに物申す!」(『中央公論』二〇〇八年一月号)。
(48)前掲第三次たばこ白書、七二ページ。
(49)同右、八四ページ。
(50)繁田正子『肺癌検診関係者や日本肺癌学会はタバコとどう対峙すべきか』(『肺癌』49巻1号、二〇〇九)一一三─二一ページ。
(51)斎藤貴男『国家に隷従せず』(ちくま文庫、二〇〇四)一六四ページ。
(52)禁酒法の歴史についてはMark E.Lender and J.K. Martin, Drinking in America(N.Y, 1987), 岡本勝『禁酒法』(講談社現代新書、一九九六)を参照。
(53)『インテリジェンス・ウイークリー』10年3月22日号(出典はGentlemen Quarterly Feb. 2010)
(54)前揭宮田、一九三ページ。原典:秦郁彦『病気の日本近代史』(二〇一一年・文藝春秋刊)第七章「肺ガンとタバコ」。なお、原著の記述は二〇〇九年前後のデータに基づいているため、著者の了解を得て最新データに変更しています。
![[キューバ産葉巻専門店] CubanCigar.jp](https://cubancigar.jp/blog/wp-content/uploads/2020/06/6211bc5a34b3936e73437face4c88e89.png)

![[キューバ産葉巻専門店] CubanCigar.jp](https://cubancigar.jp/blog/wp-content/uploads/2020/06/842522a30bddef97d178726ffb921b76.png)














































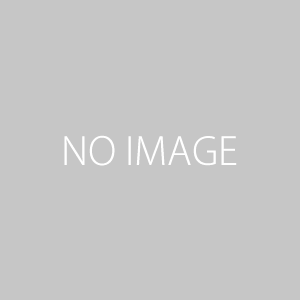




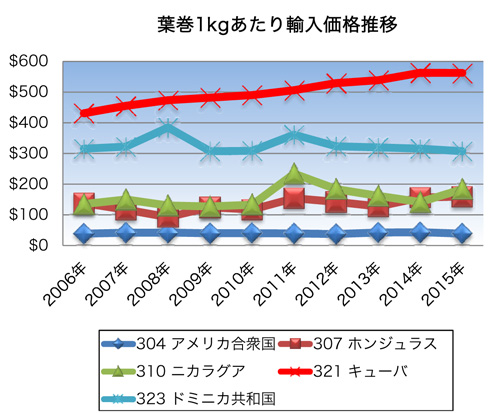











この記事へのコメントはありません。